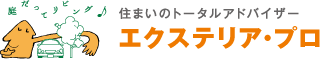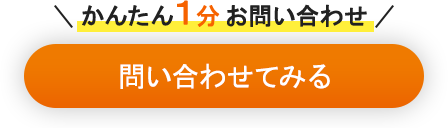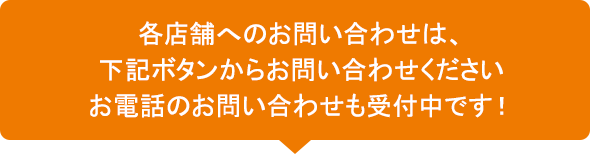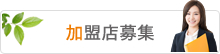防風フェンスで強風から自宅を守ろう!設置のメリットや注意点を徹底解説

新居を購入したら、住宅や庭を風害から守り美しく保ちたいと考える方は多いのではないでしょうか。
防風フェンスは、強風による被害を軽減するだけでなく、プライバシーの確保や美観の向上にも役立ちます。
本記事では、防風フェンスの種類について解説し、おすすめのフェンスも紹介します。
目次
防風フェンスはなぜ必要なのか
防風フェンスは、強風から住宅や庭の植物、駐車している車両などを守る役割を果たします。さらに、砂埃や落ち葉の侵入を防ぎ、敷地内の清潔さを保つ効果も期待できるでしょう。
日本は台風や季節風の影響を受けやすい地理的条件にあり、年間を通して強風に見舞われることが少なくありません。強風にさらされる地域では、一般的なフェンスだと強風の被害を免れない可能性があります。
住宅地では建物の間を通り抜ける風が増速することがあり、予想以上の風害をもたらすケースも珍しくないのです。
新居で快適に暮らすためには、風対策は欠かせない要素といえるでしょう。
特に台風の影響の強い九州エリアはフェンス設置の場合、フェンスの耐風圧は設置前に検討することが大切です。
防風フェンスを設置するメリット

防風フェンスの設置は、単に風を遮るだけではなく、住環境全体の質を向上させる4つのメリットがあります。
- 大切な住居や庭、車・自転車を強風から守ることができる
- 住宅の外観を綺麗に見せることができる
- 短期間で設置が可能
- 耐久性が高いので長期的に使用ができる
景観面でも優れた特徴を持ち合わせています。
大切な住居や庭、車・自転車を強風から守ることができる
防風フェンスを設置すると、強風による被害から大切な家財を守れます。
突風は屋根材や外壁を傷つけたり、庭の植物を根こそぎ倒したりする危険性をはらんでいます。
また、駐車場に停めている車には飛散物が当たって傷がつくリスクも存在するのです。
防風フェンスを適切に設置すると、設置条件やフェンスの構造次第で風速を大幅に抑えることができ、風害から住居や所有物を効果的に保護することができます。
さらに、砂埃や塵の侵入も大幅に軽減されるため、清掃の手間も省けるという点もメリットです。
住宅の外観を綺麗に見せることができる
防風フェンスは機能性だけでなく、住宅の外観を美しく見せる装飾的な役割も果たします。
素材やデザインのバリエーションが豊富で、住宅の外観や庭のコンセプトに合わせた選択が可能です。カラーバリエーションも充実しており、外壁や玄関との調和を考慮した色選びができます。
たとえば、木調のものはナチュラルな雰囲気を演出し、アルミ製のモダンなデザインは洗練された印象を与えるでしょう。つる性植物を絡ませると、緑あふれる空間の創出も可能です。
短期間で設置が可能
防風フェンスの魅力のひとつに、比較的短期間で設置できる点が挙げられます。標準的な風よけフェンスの設置は、1日から3日で完了することがほとんどです。
既製品を使用する場合は、基礎工事を含めても数日で終わるケースも少なくありません。
DIY向けの製品も多く販売されており、ホームセンターで購入して週末に自分で設置することも可能です。
事前に地盤の状態や風の強さを考慮した適切な製品選びができていれば、短時間で効果的な風対策が実現できるでしょう。新居への入居直後でも、すぐに快適な環境を整えられる点は大きなメリットです。
耐久性が高いので長期的に使用ができる
防風機能が充実したフェンスは、高い耐久性を誇る素材で製造されています。アルミ製やスチール製のフェンスは、適切なメンテナンスを行えば10~30年以上の長期使用が可能です。
樹脂製でも紫外線や雨風に強く、変色や劣化に強い製品が増えてきました。
木製タイプも、防腐・防蟻処理が施されたものであれば10年以上の寿命が期待できます。
定期的な点検とメンテナンスで、さらに長持ちさせることも可能になるでしょう。
フェンスの種類と耐風性

フェンスの種類ごとに、特徴や耐風性をまとめました。
- 風に煽られにくいメッシュタイプ
- 目隠しと防風が両立できるルーバータイプ
- すきま風も通さない目隠しタイプ
自宅の立地条件や風の強さ、求める機能性を考慮して、最適なフェンスを選びましょう。
風に煽られにくいメッシュタイプ
メッシュタイプの防風フェンスは、小さな穴が無数に開いています。風を完全に遮るのではなく一部を通過させることで全体の風圧を軽減する設計です。そのため、強風時にフェンス自体が倒壊するリスクを低減できる点が魅力です。
通気性があるため、圧迫感も少なく開放的な雰囲気を保てます。材質は主にスチールやアルミニウムが使用され、錆に強い粉体塗装や溶融亜鉛メッキ処理が施されているものが一般的です。
風速30m/秒程度の強風にも耐えられる製品が多く、台風が頻繁に来る地域でも安心して使用できるでしょう。
目隠しと防風が両立できるルーバータイプ
ルーバータイプの防風フェンスは、斜めに配置された横板により風の勢いを和らげつつ、視線をカットする機能を併せ持っています。
斜めに配置された板が風を上方向に受け流す構造になっているため、風がフェンスを直撃するのを防ぎ、風圧を軽減する効果が期待できます。
板の角度によって風の通り抜け方や視線のカット率を調整できるため、設置環境に応じた最適な設計が可能です。
内側からは外の景色を眺められるのに、外からは中が見えにくいという一方向性の視認性も大きな特徴といえるでしょう。
モダンでスタイリッシュなデザインが多く、コンテンポラリーな住宅との相性がよい点が特徴です。
すきま風も通さない目隠しタイプ
目隠しタイプの防風フェンスは、板と板の間に隙間がなく、完全に視線と風を遮断する構造で、プライバシーを最優先したい方におすすめです。防音効果も期待できるため、交通量の多い道路に面した住宅では生活騒音の軽減にも役立ちます。
隙間がほとんどないため、風をほとんど通しません。風の圧力を全て受け止める構造のため、強風が予想される地域では基礎工事をしっかり行い、強度の高い支柱を使用するなどの対策が必要です。
庭全体を包み込むように設置すれば、プライベート空間が広がります。
防風フェンスの選び方

防風フェンスは、以下を考慮して選びましょう。
- 素材で選ぶ
- 耐風圧強度で選ぶ
- 高さで選ぶ
- 支柱の本数で選ぶ
- メンテナンス性で選ぶ
重視するポイントに優先順位をつけると、選びやすくなります。
素材で選ぶ
防風フェンスの素材選びは、耐久性やデザイン、コストに直結します。
アルミ製は軽量で錆びにくく、耐久性に優れているため、メンテナンスの手間を省きたい方におすすめです。一方、スチール製は強度が高いものの、錆び止め加工が必要になることが多いでしょう。
木製は自然な風合いが魅力ですが、定期的な塗装や防腐処理が必要です。最近ではエコ素材として人気の高い樹脂製もあり、耐候性に優れ、見た目も木製に似せたものが多く登場しています。
それぞれの素材特性を把握し、自宅の環境や自分のライフスタイルに合った選択をすることが大切です。
耐風圧強度で選ぶ
防風フェンスの本来の目的を考えると、耐風圧強度は重要視すべきポイントです。一般的なフェンスの耐風圧強度は30m/秒~50m/秒の範囲で設計されています。
台風が頻繁に来る地域や海岸沿いなどは、最低でも40m/秒以上の耐風圧強度を持つ製品を選ぶのがおすすめです。
メーカーの仕様書には「設計風速」や「耐風圧」として数値が記載されていますので、確認しましょう。
風が抜ける構造になっているメッシュタイプは、風圧を受けにくいため高い耐風性を発揮します。
高さで選ぶ
フェンスの高さは、防風効果とプライバシー保護のバランスを考慮して選びましょう。
一般的な住宅用防風フェンスの高さは、0.8m~2.0mの範囲が主流です。
低めの0.8m~1.2m程度のフェンスは、視界を遮らずに風の影響を軽減したい場合に適しています。一方、1.5m以上の高さがあれば、風だけでなく視線もしっかりとカットできるため、プライバシーの確保も同時に実現できるでしょう。
高さがあるほど風の影響を受けやすくなります。高いフェンスを選ぶ場合は、より強固な基礎工事や支柱の強化が必要になることを忘れないようにしましょう。
支柱の本数で選ぶ
安定性と耐久性を高めるには、支柱の本数を増やすのがおすすめです。
支柱の間隔が狭いほど全体の強度が増し、強風に対する抵抗力が高まります。標準的な間隔は1.8m~2.0mですが、風の強い地域では1.5m以下に設定することで安全性が向上するでしょう。
コーナー部分や端部には必ず支柱を設置し、補強することが大切です。メーカーによっては、地域の風速に応じた支柱の推奨間隔を示しているケースもあります。
基礎部分の施工方法も重要で、コンクリート埋め込み式や、簡易的な設置が可能なブロック据え置き式など、設置環境に応じた選択が必要です。
メンテナンス性で選ぶ
長期にわたって防風フェンスの機能と美観を維持するためには、メンテナンス性も重要な選択基準です。
アルミ製は基本的にはメンテナンスフリーで、年に1~2回の水洗いで汚れを落とすだけで長持ちします。
一方、スチール製は5~7年に一度の塗り直しが必要になることがあるでしょう。木製は1~3年ごとに防腐剤や塗装の塗り直しが必要で、メンテナンスの手間がかかります。
樹脂製は比較的メンテナンスが容易ですが、長年の使用で色あせする場合があるため、定期的な点検が望ましいでしょう。
自分のライフスタイルや将来のメンテナンスにかけられる時間や費用を考慮して、無理なく維持できる素材を選ぶことが大切です。
防風フェンスのおすすめ商品3選

ここからは、初心者でも扱いやすいおすすめフェンスを3種紹介します。
- LIXIL フェンスAB TM2型
- YKK AP ルシアス フェンス
- 三協アルミ シャトレナⅡ
デザイン性、機能性、耐久性のバランスが取れており、初めて防風フェンスを導入する方にも安心して選べるものばかりです。
LIXIL フェンスAB TM2型
TM2型は完全な目隠しを実現しており、外部からの視線を完全に遮断するタイプのフェンスです。
フェンスは50種類以上の豊富なデザイン、色などが揃っており、様々な要望、ニーズにマッチしたラインナップとなっております。
LIXILのフェンスAB TM2型は、シンプルながら洗練されたデザインと高い実用性で人気を集めています。
横板の間にわずかな隙間を設けたセミクローズドタイプで、風圧を和らげつつも高い防風効果を発揮します。
アルミ製のため非常に軽量で、腐食の心配もほとんどありません。標準的な耐風圧は風速34m/秒相当で、一般的な住宅地での使用に十分な強度を持っています。
また、柱のピッチを1メートルにすることで、耐風圧を42M・秒に上げることも可能です。
YKK AP ルシアス フェンス
YKK APのルシアスフェンスは、高いデザイン性と機能性を両立させたフェンスです。
22種類のデザインから選択可能で、ナチュラル、シック、シンプル、エレガント、和風、洋風など、さまざまな住宅スタイルに合わせたデザインが用意されています。
特にルーバータイプは風の通り道を確保しつつ、視線をカットできるバランスの良さが支持されるポイントです。
アルミ形材の厚みがあり、高い剛性と耐久性を誇る点も魅力。表面処理技術にも定評があり、長期間美しい外観を保てます。
三協アルミ シャトレナⅡ
シャトレナⅡは、フレームレスでフラットなデザインを採用しており、すっきりとした木調の外観が特徴です。
下桟すき間を15mmにすると、下桟すき間カバーを付けることなくブロックとのすき間を小さくできます。
上下桟が木調色となっている「プレミアムタイプ」は、高級感あふれる雰囲気が演出できるでしょう。
カラーバリエーションも豊富で、薄い色はスタイリッシュに、濃い色は重厚感あふれる存在感で住宅を彩ります。
防風フェンス設置の注意点
防風フェンス設置の際に特に注意すべき4つのポイントを解説します。
- 選ぶフェンス次第で金額がかさむことがある
- 強度の高いものを選ぶ
- 柱基礎はしっかりとメーカー基準工事を守って施工する
- 天候や排気ガスによって汚れるので定期的な清掃が必要
失敗やトラブルを未然に防ぐために、丁寧に確認しましょう。
選ぶフェンス次第で金額がかさむことがある
防風フェンスの価格は、素材や品質、機能性によって変動します。
住宅用フェンスの価格帯は、1メートルあたりおおよそ10,000円~30,000円程度ですが、高級素材や特殊機能を備えたものになると、50,000円を超えることも珍しくありません。
既存フェンスの撤去や地盤改良など、基本工事費に含まれていない追加工事が必要になると、予想以上に費用がかさむでしょう。
デザイン性の高いオーダーメイド品を選ぶと、標準品の1.5~2倍の価格になることもあります。
強度の高いものを選ぶ
台風の常襲地域や海岸沿い、高台など風の影響を強く受ける場所では、耐風圧性能の高い製品を選ぶことが不可欠といえるでしょう。
安価な製品は一見コスト面で魅力的に感じられますが、強風で倒壊してしまっては本末転倒です。
製品選びの際は、メーカーが公表している耐風圧強度の数値を確認し、地域の気候に対応できるものを選びましょう。
また、支柱の強度や基礎工事の仕様も確認すべきポイントです。
柱基礎はしっかりとメーカー基準工事を守って施工する
柱基礎の施工品質は、防風フェンスの強度と耐久性を左右します。
どれほど高品質なフェンスを選んでも、基礎が不十分であれば強風で倒壊するリスクが高まります。
メーカーが指定する基礎の寸法や深さ、コンクリートの配合比率などの基準を厳守しましょう。
一般的に独立基礎の場合、柱は地中に30cm以上埋め込み、直径20cm以上のコンクリート基礎で固定するのが標準とされています。
地盤の状態によっては、補強工事が必要な場合もあるでしょう。
DIYでの設置を検討している場合は、基礎工事の難易度が高いことを認識し、専門業者への依頼も視野に入れてください。
天候や排気ガスによって汚れるので定期的な清掃が必要
防風フェンスは屋外に設置されるため、雨や風、排気ガス、花粉などの影響で徐々に汚れが蓄積します。
白や明るい色のフェンスは汚れが目立ちやすく、美観を損なうことがあるでしょう。
アルミ製やスチール製のフェンスは、年に2~3回程度の水洗いできれいに保てます。木製フェンスの場合は、水洗いに加えて1~3年に一度の防腐剤や塗装の塗り直しが必要です。
海岸沿いの塩害地域では、塩分の付着による腐食が進行しやすいため、より頻繁なメンテナンスが求められます。
防風フェンスの設置に関するよくある質問
ここでは、防風フェンスの設置に関するよくある質問と回答を、3つ厳選しました。
防風フェンスの効果的な高さや設置位置はありますか?
標準的な高さは1.5m~2.0mとされており、この高さがあれば住宅敷地内の風の影響を軽減できるでしょう。
強風が問題となる地域では、2.0mを超える高さもおすすめです。
風の通り道となる隣地との境界や、特に風の影響を受けやすいコーナー部分に優先的に設置すると効果的です。地形によって風の流れが変わることも考慮に入れましょう。
防風フェンスの素材にはどんな種類がありますか?
防風フェンスの主な素材には、アルミ、スチール、木材、樹脂などがあります。
アルミ製は軽量で錆びにくく、メンテナンスが容易なため人気です。寿命は15~20年程度で、カラーバリエーションも豊富です。
スチール製は強度に優れていますが、錆びやすいため防錆処理が施されたものを選ぶ必要があるでしょう。木製は自然な風合いが魅力ですが、定期的な塗装や防腐処理が必要で、寿命は7~10年程度です。
しかし、デザインが少なく、意匠性を求める方には不向きかもしれません。
樹脂製は、軽量で加工性に優れ、木目調のデザインも実現可能です。耐候性も高く、メンテナンスの手間も少ないのが特徴といえるでしょう。
欠点は樹脂製な為、色あせ等が起きてしまいやすいという点です。
防風フェンスの設置にはどれくらいの料金がかかりますか?
防風フェンスの設置費用は、選ぶ製品の種類や設置する長さ、基礎工事の内容によって変動します。
一般的な住宅用防風フェンスの場合、フェンス本体の価格は1メートルあたり10,000円~30,000円程度です。これに施工費が加わり、基本的な工事費用は1メートルあたり5,000円~15,000円が目安となります。
一般的な住宅の敷地周囲20メートルにフェンスを設置する場合、本体と基本工事を合わせて30万円~90万円程度が相場といえるでしょう。
ただし、既存フェンスの撤去や地盤改良が必要な場合は、さらに費用がかかります。
まとめ
防風フェンスは、強風から住宅や庭を守るだけでなく、プライバシーの確保や外観の美化など、多くのメリットをもたらす設備です。
防風対策は住環境の快適さや住宅の寿命を左右します。フェンス選びでは、立地条件や予算、デザイン性などを総合的に考慮し、後悔のない選択をすることが大切です。
設置後のメンテナンスも忘れずに行い、長く美しく機能的な状態を保ちましょう。
快適で安心な住環境づくりの一助として、本記事を参考にフェンスの設置を検討してみてください。