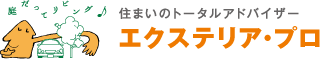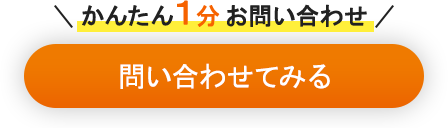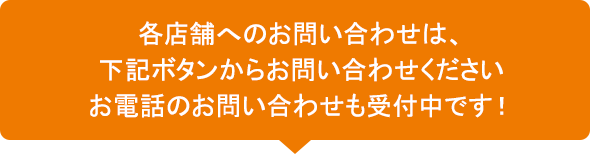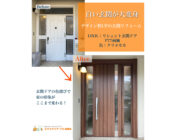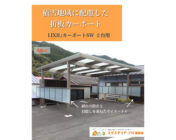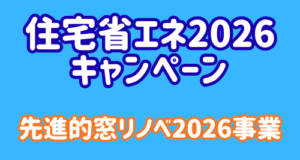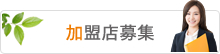ウッドデッキの設置にかかる費用はいくら?メリットやデメリットについても解説

在宅時間が増えた昨今、庭先にウッドデッキを設置してもう一つのリビングを楽しむ家庭が急増しています。しかし、天然木と人工木で相場が大きく異なり、基礎工法やオプションの有無でも総額が変動するため、具体的な費用感がつかみにくいのが実情です。
今回は㎡あたりの目安価格から、費用を左右する五大要因、代表的な製品と選定のコツまで体系的に解説します。メリット・デメリットや法規制、DIY可否などの疑問にも触れるので、初めてのウッドデッキ計画でも安心して予算組みができるようになるでしょう。
目次
ウッドデッキの設置にかかる費用はどれくらい?
ウッドデッキの総費用は、素材と面積および材質や基礎仕様の選択次第で変動幅が広がります。
ここからは「天然木」と「人工木」に分けて、㎡単価と特徴を詳しく見ていきましょう。
天然木の場合
杉やSPF(※1)などのソフトウッドは㎡あたり1万5千円〜3万円で導入しやすい一方、耐久年数は5年前後と短く、2〜3年ごとの塗装やビス増し締めが欠かせません。
ウリンやイペなどのハードウッドは㎡あたり3万〜4万円と高価ですが、油分が豊富で湿気やシロアリに強く、15年以上メンテナンスフリーで使える例もあります。
香りや経年変化を楽しめる反面、加工難度と工賃が上がる点に注意し、黒ずみ防止のためステンレスビスや専用オイルを選定して美観を保ちましょう。
※1 スプルース、パイン、ファーの3つの木材の頭文字をとったもの。成長が早いので比較的価格が安い傾向にある。
人工木の場合
木粉と高耐候樹脂を押出成形した人工木は㎡あたり1万〜4万円が標準価格です。反りやささくれがほとんど出ず素足でも安全に歩け、オイル塗装が不要なためランニングコストを大幅に削減できます。
内部まで同色の一体成形品なら傷が付いても目立ちにくく、数十年単位の耐久実績を持つ製品も存在します。
ただし、真夏の直射日光下では表面温度が上がりやすいため、ペットや子どもが素足で歩く場合は遮熱タイプやシェードの併用を検討すると安心です。
費用を左右する要因

ウッドデッキの最終見積額は「どこに設置し、どんな形状・基礎・材料を選び、誰が施工し、どの設備を同時に加えるか」で大きく変動します。
ここからは費用を左右する要因について細かく説明するので、ウッドデッキを設置する前にどのくらいの費用がかかるのかを計算するための参考にしてみてください。
面積・形状
デッキ費用は基本的に㎡単価×面積で算出しますが、面積が増えれば搬入車両や職人人数も増加し、人件費が比例して上がります。
さらに台形・L字・コの字など複雑形状ではカットロスや端材処分費が発生し、階段や段差を組み込むと支持脚の種類が増えて工賃も跳ね上がります。できるだけシンプルな長方形を採用し、ステップを独立ユニット化すれば余尺を抑えられます。
また、設置方向を外壁と平行にすると根太位置が単純化し、標準寸法材を活用できるため、材料ロスと納期遅延を同時に減らせます。
素材
ウッドデッキ材の価格帯はソフトウッド<人工木<ハードウッドの順で上昇します。ソフトウッドは初期投資を抑えられますが、塗装更新や交換頻度が高く、長期合計では割高になりがちです。
人工木は中空板が安価、無垢板は高価ながら強度と歩行音の静かさに優れ、重い家具やプールを置く家庭に適します。
ハードウッドは耐久性が最も高いものの重量があり、基礎補強費が跳ねる点に注意が必要です。選定時は初期費用・メンテナンス頻度・期待寿命を表で比較し、10年総コストで最適解を導きましょう。
基礎工法
基礎は束石だけの簡易工法、地面に独立基礎を打つ工法、住宅基礎と一体化する布基礎に大別されます。束石工法は㎡あたり6,000円前後と安価ですが、不陸調整(※1)が難しく凍害地域では沈下や傾斜のリスクがあります。
独立基礎は鉄筋組みとコンクリートで㎡あたり1万円程度の上乗せとなりますが、床下通気と耐震性を確保でき、長期メンテ費を抑えられます。布基礎はさらにコストアップしますが外周を一周するため防草効果が高く、床下への動物侵入も防げる点で安心です。
※1 床や壁などの表面に生じた凹凸や傾きを平らにする作業のこと
施工方法
施工方法はプロへの一括発注とDIYに大別されます。プロ施工は㎡あたり4万〜6万円で水平調整・防水処理・保証まで含まれ、仕上がり品質と安全性が高い点がメリットです。
DIYは材料費を半額近くに抑えられますが、工具レンタル費や測量ミスによる再購入リスクが加わります。休日や体力、技術習得のコストを見積もったうえで方式を選びましょう。
なお、プロに下地だけ依頼し床板をDIYするハイブリッド方式もあり、予算と体験価値のバランスが取りやすい方法として注目されています。
オプション
手すり・ステップ・パーゴラ・照明・物干し金物などのオプションは、本体価格の2〜5割を追加する場合があります。特に手すりは高さと強度規定を満たす必要があり、構造計算と取付工賃がコストを押し上げる傾向です。
照明と屋外コンセントは後付け配線が難しいため、最初から電源ルートを確保しておくと無駄な再工事を避けられます。将来の活用シーンを想定し必要機能を優先順位で整理し、一括見積もりで割安に導入しましょう。
パーゴラにシェードレールを備えておけば、後日オーニングを追加する際も金物を流用できるため、総コストの抑制に役立ちます。
ウッドデッキを設置するメリット

ウッドデッキは庭を単なる鑑賞スペースから家族が能動的に過ごす第2のリビングへ昇華させます。
以下では生活空間の拡張や動線改善、景観向上など六つの具体的メリットを紹介し、導入効果をイメージできるよう解説します。
生活空間を屋外へ拡張し多目的に活用できる
デッキにテーブルセットを置けば朝食やカフェタイムの屋外テラスになり、ヨガマットを広げればワークアウトスペース、ビニールプールを設置すれば子ども向け簡易リゾートへ早変わりします。
屋根やシェードを併用すれば季節や天候に合わせて利用シーンを柔軟に切り替えられ、限られた居住面積でも体験のバリエーションを大幅に増やせる点が大きな魅力です。
また、屋外で過ごす時間が増えることで自然光や風を取り込みやすくなり、在宅ワークのリフレッシュや子どもの五感発達にもプラスに働きます。夜間は照明を組み合わせればアウトドアバーや星空観察の舞台にも変身します。
室内外の一体感が生まれ居住性・動線が向上する
リビングとデッキの床高を揃えれば段差が消え、屋内外の動線がシームレスにつながります。洗濯物やガーデニング用品の持ち運びが楽になり、キッチンと庭を往復する際も足取りがスムーズです。
ガラス戸越しの視界が抜けることで視覚的奥行きが倍増し、室内側の採光も向上します。結果として同じ床面積でも開放感が高まり、在宅時間が長い家庭ほどストレス軽減効果を実感できます。
さらに、車いすやベビーカーでも無理なく出入りでき、ユニバーサルデザインの観点からも優秀です。雨の日でも屋根を延長しておけば濡れずに出入りでき、玄関以外の第二の導線として防災時の避難経路を兼ねる利点も生まれます。
また、室内と庭の段差を調整できるので気軽に庭と室内を出入りできるのもメリットもあります。
家族や友人とのコミュニケーションを促進する憩いの場になる
屋外に設けたウッドデッキは開放感があるため心理的ハードルを下げ、家族やゲストが自然と集まる社交ステージになります。BBQグリルや焚き火台を設置しても煙や匂いが室内にこもらず、後片付けも水洗いで簡単です。
子どもたちはキッズプールや水鉄砲で遊び、大人はハイチェアでカクテルを楽しむなど、年齢差を超えて同じ時間を共有できます。
さらに、プロジェクターやスピーカーを持ち込めば屋外シアターやライブステージとして機能し、家にいながらイベント気分を味わえます。こうした非日常体験が会話を弾ませ、家族間の絆や友人との交友を深める効果が期待できます。
自然素材の温もりで景観が向上する
木目や節の豊かな表情が外壁や植栽と調和し、人工的な住宅外観に柔らかなアクセントを添えます。特にハードウッドは紫外線で徐々にシルバーグレーへ経年変化し、アンティーク家具のような深みを演出するため、日ごとに味わいが増す外構を楽しめます。
人工木でもエンボス加工や濃淡配色を選べば天然材に近い質感を得られ、メンテナンス性と意匠性を両立可能です。
加えて床面がフラットになることでガーデンファニチャーの安定感が増し、花壇や照明の配置が映えるため、夜間ライトアップも含めたトータルコーディネートで住宅の資産価値向上につながります。
子どもやペットを遊ばせられる
デッキは地盤より数十センチ高く、庭土の泥はねや雑草を気にせず安全に遊べるクリーンな遊び場となります。床板の隙間を狭くすれば小型犬や猫の爪が挟まりにくく、滑り止め加工を施すことで転倒リスクも低減されます。
近年では、人工木のデッキであればペット用を用意しているメーカーもあるため、ペットを遊ばせるという方はペット用の導入を検討するのがおすすめです。
プールや砂場を置いても排水が容易で、人工木ならささくれや防腐剤の溶出がなくアレルギー対策としても安心です。
また、デッキ下に防虫ネットを張ればハチや蚊の発生を抑制でき、保護者はリビングから目を離さずに子どもの成長を見守れます。夜間も足元照明を組み合わせれば視認性が向上し、帰宅の遅い家族がペットを運動させる際にも重宝します。
ガーデニングを楽しめる
ウッドデッキは立体的なレイアウトが可能で、プランター台やフェンスにハンギングバスケットを設置すれば、地面を汚さずに多層的な植栽を楽しめます。
床が水平なので土や水がこぼれても掃除が簡単で、車椅子や高齢者でも腰への負担を軽減しながら園芸作業が行えます。床下通気を妨げない脚付きプランターを選べば木材の腐朽リスクを抑えつつ、ハーブやトマトなど食用植物のキッチンガーデン化も容易です。
さらに、照明や自動散水タイマーと連動させれば、夜景演出と省力管理を両立し、ガーデニングの楽しみを一年中持続できます。季節ごとの花苗を交換するだけで景観が刷新され、居住者も来客も視覚的な変化を楽しめます。
ウッドデッキを設置するデメリット

ウッドデッキは屋外リビングとして人気ですが、導入には維持費や劣化対策など見落としがちな危険が潜んでいます。
予算と手間を正しく把握しないと早期に後悔する恐れがあります。ここでは代表的な6つのデメリットをご紹介するので、ひとつずつチェックしていきましょう。
維持費がかかる
天然木では年1回の浸透性オイル塗布とビス増し締めが必須で材料費と工具レンタル費が継続的に発生します。人工木も高圧洗浄機と中性洗剤を用いた洗浄や留め具点検が欠かせないので、維持予算に組み込むと想定外の出費を抑えられます。
また、塗装色を変更する際は旧塗膜除去費も追加されるため初期設計段階で色調を固めることが経済的です。
雨が多い地域ではメンテ周期が短縮しランニングコストがさらに跳ね上がるため気候条件も踏まえて計画しましょう。外部業者に委託する場合は出張費相当も発生します。
経年劣化による変色・ささくれ・反りのリスクがある
紫外線や酸性雨にさらされる天然木は数年で銀白化し表面割れやささくれが発生します。硬質材でも乾燥収縮差で反りが起こり、床高や隙間が不均等になると転倒危険が増加します。
人工木は顔料退色こそ緩やかですが5〜10年で部分的な色むらが現れ、傷補修用クレヨンや交換板を用意しておくと安心です。いずれも定期点検と早期補修により寿命を延ばせるため理念だけでなく運用体制を組む必要があります。
また、高温乾燥で収縮を繰り返すと留めビス周辺にクラックが入り雨水侵入源となるため、コーキングやステンレスビスへの更新が劣化抑制に寄与します。
天候によって使用頻度が左右される
晴天時はアウトドアリビングとして活躍しますが雨天や降雪期には滑りやすく、真夏は直射日光で表面温度が60℃近くまで上昇し素足では歩けません。
遮熱板やシェードを設けても日射角度が変わる時間帯では効果が薄れ、結局季節限定の利用に落ち着く家庭が少なくありません。天気連動型の照明や屋根を後付けする場合は配線と柱立て費がかさみ、初期計画より費用対効果が低下する点に注意が必要です。
また、長雨が続くとカビ臭発生や床下湿度上昇でシロアリ誘引リスクが高まるため、利用予定月と降水傾向を照合し屋根や撥水シートの導入可否を検討しましょう。
床下など掃除が難しい箇所がある
ウッドデッキ下は地表と床板に挟まれた閉鎖空間となり、落葉や砂埃が風で溜まりやすく湿気がこもります。換気が滞るとカビやキノコが発生し、最悪の場合はシロアリが巣食い構造材を空洞化させます。
点検口や掃除口を設けてもホースやブロワーを差し込む程度の作業しかできず完全除去は困難です。年1回の高床ジャッキアップ掃除を業者に頼むと費用が追加されるため、計画段階で落葉が少ない位置を選ぶなど予防的配置が重要です。
さらに、ペットボトルや玩具が隙間から落下すると回収に床板脱着が必要となり、都度工賃が重なることもあるので注意しましょう。
周囲からウッドデッキが見えてしまう可能性がある
リビング床面と同レベルで設置すると地盤より30cm以上高くなるため隣家や道路から室内よりもデッキ側が先に視線に入ります。袖壁やボーダーフェンスを追加すると材料費と基礎補強費が高額になる場合があります。
植栽で目隠しする方法もありますが成長待ちの期間は視線が続き、防風網やシェードを臨時設置する手間が増えます。
光と風を遮り過ぎると通気性が落ち腐朽を促進するため、視線カットと空気循環を両立する開口率設計が求められます。事前に立面図で周囲視線をシミュレーションすると追加費の抑制につながります。
解体・廃棄時に追加費用・手間が発生する
ウッドデッキは長尺部材と重量束柱で構成されるため解体時に人手と電動工具が必要です。自治体によっては人工木を可燃ごみとして回収せず指定業者への運搬を求められ、トラックチャーターと処分費で初期費用に追加で請求される事例があります。
コンクリート基礎を採用した場合は斫り工事と産業廃棄物運搬費が上乗せされ、中古市場で部材を譲渡する方法もありますが分解梱包の手間と送料がかさむため実益は限定的です。
将来的な撤去を見据えるなら組立式金属束や再利用可能な置き基礎を選択するとコストと環境負荷を軽減できます。
ウッドデッキのおすすめ製品3選

各メーカーは素材配合や遮熱技術、下地構造の剛性向上など多角的な改良を重ね、価格帯も様々なため選択肢が豊富です。
まずは機能性とコスパのバランスが優れた3製品を具体的に見ていきましょう。
LIXIL デッキDC
独立気泡を含む低熱伝導樹脂が直射日光の熱を逃がし、試験値で一般的な人工木より温度を約4℃低減します。素足利用が多い家庭でも真夏の火傷リスクを抑えられる点が魅力です。
床板は硬質エンボス加工で傷と汚れに強く、ホース洗浄だけで美観を維持できます。色調は6色と高強度幕板を組み合わせればモダンからナチュラルまで幅広い外観に対応できます。
また、使用している表面材はペットが滑りにくい素材のため、ペットを遊ばせたいという方にもおすすめです。
YKKAP リウッドデッキ 200
木粉とポリプロピレンを高圧混練したリウッド材は吸水率が低く、水濡れによる膨張や腐朽菌の侵入を防ぎます。床板内部まで着色されているため傷が付いても色むらが生じにくく、塗装メンテナンス不要でランニングコストを削減できます。
別売フラットライン照明と連動すれば夜間デッキライトで空間演出が可能です。床下換気部材もセット化されており、シロアリ対策面でも安心感が高まります。
三協アルミ ヴィラウッド
高耐候樹脂層の床板が紫外線や雨水による色あせを抑えます。素材にアルミ形材を採用することで剛性が向上し、シロアリなどの被害も防ぐことができる設計です。
オプションのパーゴラフレームを組み合わせればシェードや照明を統合でき、屋外ラウンジへ発展させる拡張性も魅力です。床下配線ダクトが標準で電源確保も容易です。
ウッドデッキの設置を失敗しないためのポイント

ウッドデッキを長く快適に使うには、地盤・法規・素材・構造・防蟻という5つの技術項目を設計段階で精査し、追加工事や施工不良を未然に防ぐことが肝心です。
以下のポイントをチェックし、見積もり前にリスクと対策を整理しておきましょう。
設置場所の地盤と基礎強度を確認しておく
軟弱地盤で束柱が沈下すると床面が傾きビス抜けや板割れに直結します。専門業者に地耐力を確認してもらい、必要なら砕石転圧+独立基礎や布基礎で支持力を底上げすると良いでしょう。
新築住宅だったら地盤調査しているため、その際の地盤調査報告書を確認してください。
設置方法としては束石をしっかり固定するか、束柱を埋め込む方法が多く、最近では土間コンクリートを敷いてその上に設置する方法があり、床下スペースを物置スペースとして活用する方も増えております。
建築基準法・境界離隔など法規制を事前に調査する
床面高さが1mを超えれば工作物確認申請が必要となる自治体が多く、防火地域では不燃材仕様や延焼ライン外への配置変更を求められる場合があります。
隣地境界から50cm以上の離隔や高さ2mを超える手すりの風圧強度など細則も多いため、役所の建築指導課で設計図・仕様書を提示し、適合確認済証を取得してから発注すると後戻りコストを回避できます。
目的に合った床材を選ぶ
裸足で過ごすテラス重視なら遮熱樹脂を含む人工木、ガーデンファイヤーピットを置くアウトドアリビングなら耐火性と板交換の容易さを兼ね備えたハードウッドが最適です。
ペットがいるならノンスリップ加工板を選び、商用利用で客席を設ける場合は防炎認定材料を選ぶのがおすすめです。用途と維持費のバランスを事前に数値比較しましょう。
使用目的に応じた耐荷重を計算しておく
一般の歩行荷重は180kg/m²が基準とされていますが、ビニールプールや大型ジャグジーを設置するなら大きさに応じた耐荷重を計算しておくようにしましょう。
梁や大引きを増すか束柱を増設するとたわみが抑えられ、長期使用でも床鳴りやビス緩みを防げます。
床下通気を確保しシロアリ防除を施す
床下換気口やデッキ用ベンチレーターを塞がない位置に束柱を配置し、最低150mmの離床を確保して湿気を逃がします。束柱基部にホウ酸塗布+防蟻テープを巻くと薬剤流出が少なく、10年以上効果が持続します。
さらに、床下に防虫ネットを張り落葉侵入を抑制することでカビや羽アリの発生源を遮断し、補修費と健康被害のリスクを同時に低減できます。
また、サッシメーカーの人工木デッキであれば束柱はアルミなのでシロアリの心配は不要です。
ウッドデッキの費用に関するよくある質問

最後に、施主が見積もり前後で抱きやすい3つの疑問をQ&A形式でご紹介いたします。
ウッドデッキを設置するにあたって注意する法律はありますか?
高さが1mを超える場合や敷地境界に近接する場合は工作物扱いとなり、自治体によって建築確認が必要です。
また、防火地域では延焼ライン内のデッキ材に不燃材指定が求められることがあります。事前に建築士や役所に相談し、図面と仕様書を添えて確認を取りましょう。
天然木と人工木はどちらがおすすめですか?
風合い重視なら天然木、メンテナンス軽減と総コスト優先なら人工木が適しています。
耐用年数と維持費を試算し、将来のライフスタイル変化まで見据えて選択するのが賢明です。
ウッドデッキはDIYでも作れますか?
キット商品を利用すればDIYも可能で、材料費を削減できます。
ただし、水平調整や根太固定に熟練が必要で、施工ミスによる再購入や怪我のリスクが伴います。休日と体力に余裕があり、電動工具の取り扱い経験がある場合に限定して検討すると良いでしょう。
まとめ
ウッドデッキの設置費用は素材・面積・基礎・施工方法・オプションで上下し、㎡あたり10,000円台〜40,000円台まで幅があります。長期視点では人工木がメンテナンスを含めた総コストを抑えやすく、天然木は経年変化という唯一無二の味わいが魅力です。
人工木でも天然木に近い風合いを施された商品もありますので、自分に合った商品を選ぶことが大事です。
地盤・法規・耐荷重・防蟻などの下準備を怠らなければ、ウッドデッキは暮らしを豊かにする強力な屋外リビングとして長く活躍してくれるでしょう。