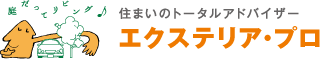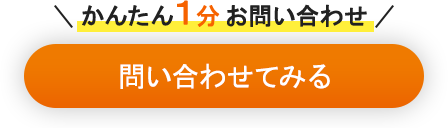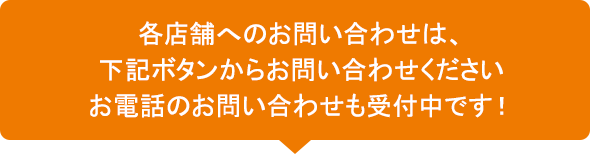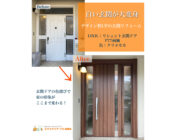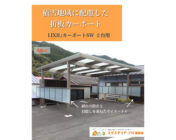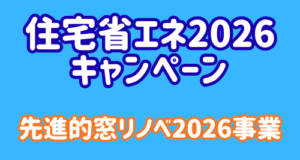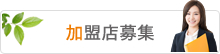愛犬を安心して庭で飼うためにはフェンスの設置がおすすめ!メリットや選び方も解説

庭で犬をのびのびと遊ばせることができれば、散歩に行けない時の代わりになったり犬のストレス解消になったりして、愛犬との生活がより充実するでしょう。
しかし、そのままの庭では愛犬が脱走したり、通行人や近隣の動物とトラブルになったりするリスクがあります。
そこでおすすめなのがフェンスの設置です。
本記事では、愛犬のためのフェンス設置のメリットや、素材選びのポイント、おすすめ商品など、犬を飼っている方、これから犬を迎える方に役立つ情報をご紹介します。
愛犬も飼い主も安心して快適に暮らせる住空間づくりの参考にしてください。
目次
愛犬のためにフェンスを設置するメリット

犬のいる家庭でフェンスを設置するメリットは、主に3つあります。
- 庭で放し飼いをすることができる
- 犬の飛び出しによる事故を防ぐことができる
- 脱走をするリスクを下げられる
飼い主と愛犬、近隣住民の共生環境が整い、安心して犬を飼えるでしょう。
庭で放し飼いをすることができる
フェンスを設置すると、愛犬を庭で安全に放し飼いできます。
リードにつながれることなく自由に動き回れることは、犬にとって大きなストレス解消になるでしょう。活発な犬種は、十分な運動スペースが必要であり、フェンスで囲まれた庭は理想の環境です。
犬が走り回る庭というと、広大な庭を想像するかもしれませんがそうではありません。
狭い庭でも、リードなしで土の上を自由に動き回れるスペースがあるとある程度の運動量を確保できます。
飼い主にとっても、常に目を離せない状況から解放され、家事や仕事をしながらでも愛犬を安全に遊ばせておけるのは大きなメリットです。
犬の飛び出しによる事故を防ぐことができる
フェンスがあれば、犬が突然走り出しても外に出ていくリスクが軽減できます。犬は猫や小動物、車など予期せぬ刺激に反応して、突然走り出すことがあります。
フェンスがなければ、びっくりした時に外へ走り出してしまうでしょう。交通量の多い道路に面した家では、交通事故に遭う危険性が高まります。また、知らない人や他の犬に突進して噛み付いたりすることも考えられます。
こうした事故は、愛犬の命を危険にさらすだけでなく、第三者へのケガや物損につながる可能性もあるため未然に防がなければなりません。
脱走をするリスクを下げられる
犬は好奇心旺盛で探索本能が強いため、隙があれば脱走しようとする傾向があります。脱走してしまった犬は、迷子になったり、事故に遭ったり、ほかの動物と遭遇して怪我をしたりする危険性があります。また、見知らぬ人に拾われてしまうかもしれません。
フェンスで愛犬の行動範囲を安全に制限すると、飼い主は常に監視していなくても安心して過ごせるでしょう。
脱走防止は、近隣住民との良好な関係を保つためにも必要です。
ハスキーやビーグルなど、特に脱走傾向の強い犬種を飼っている場合はしっかりとしたフェンスが不可欠です。
適切なフェンスを設置することで、上記のリスクを大幅に減らせます。
犬のためのフェンスにおすすめの素材

犬のいる家に適したフェンスの素材は、下記のとおりです。
- 木製のフェンス
- アルミ製のフェンス
- 樹脂製のフェンス
フェンスの素材選びは、耐久性や安全性、メンテナンス性に影響するため、愛犬の種類や性格、住環境に合わせて最適な素材を選ぶことが大切です。
木製のフェンス
木製のフェンスは目隠し効果が高く、犬が外部からの刺激に反応しにくくなることがメリットです。
木製フェンスは自然な風合いが魅力で、庭の景観と調和しやすく、温かみのある雰囲気を作れます。
しかし、経年劣化や腐食のリスクがあるため、定期的なメンテナンスが必要です。防腐処理された木材を選ぶと、耐久性を高められるでしょう。
大型犬や噛む癖のある犬の場合は、木材が傷つきやすいため、補強が必要になることもあります。設置後は定期的に塗装を塗り直すなどのケアが必要ですが、DIYで修繕しやすいのも木製フェンスのメリットです。
デザインのバリエーションも豊富で、縦格子や横板などさまざまなスタイルから選べます。
アルミ製のフェンス
アルミ製フェンスは、軽量でありながら強度と耐久性に優れているため、犬用フェンスとしても高い機能性が期待できます。
大型犬が体当たりするような場合でも変形しにくく、隙間の狭いものを選べば小型犬が隙間から脱走するリスクも低減できるでしょう。
デザインやカラーが豊富で、住宅の外観に合わせやすい点もメリットです。
錆びにくく腐食に強いため、メンテナンス性に優れており湿気の多い地域や海沿いの住宅でも使いやすいフェンスです。
樹脂製のフェンス
樹脂製フェンスは、軽量で扱いやすく、水や湿気に強い点が特徴です。
基本的にメンテナンスフリーで、定期的に水洗いをするだけで済みます。塗装や防腐剤の塗布が不要なため、手間がかかりません。
木材のような見た目を再現したものも多く、天然木の温かみを感じさせながらもメンテナンスの手間が少ないというメリットがあります。
犬が噛んでも破片が出にくいため、怪我のリスクを軽減できるでしょう。環境に配慮したリサイクル素材を使用した製品も増えており、エコ志向の飼い主にも支持されています。
犬のためのフェンスを選ぶ際のポイント

愛犬のためのフェンスを選ぶ際は、下記を考慮して選びます。
- 飛び越えられない高さにする
- ぶつかってもフェンスが壊れないような強度のものにする
- 柱のピッチが狭いものを選ぶ
- 脱走しないように隙間の狭いものにする
- 取り付けた後のメンテナンス性の高いメーカーを選ぶ
将来的な犬の成長や家族構成の変化も視野に入れ、長期的な視点で選びましょう。
飛び越えられない高さにする
高さの目安は、1.2m~1.5mほどです。助走ができる広い庭や、ジャンプ力の高い大型犬の場合は1.8m以上あるのが望ましいでしょう。
犬は驚いたり興奮したりすると通常の能力以上のジャンプをすることがあるため、余裕を持った高さ設定が安心です。また、子犬の成長も見越して、成犬時の能力に合わせた高さにすることをおすすめします。
植木鉢や椅子のような、犬が足場にできるような物を置かないことも心がけましょう。
ぶつかってもフェンスが壊れないような強度のものにする
活発な犬は、走り回ったり遊んだりする際にフェンスに体当たりすることがあります。若い犬や大型犬の場合、フェンスにぶつかった際の衝撃は想像以上に大きくなるでしょう。
そのため、フェンスは愛犬の体重や活動量に耐えられる強度を持ったものを選ぶことが大切です。
強度が不足すると、フェンスが変形したり破損したりするだけでなく、犬が怪我をするリスクも高まります。
アルミ製や鉄製のフェンスは強度が高く、大型犬の衝撃にも耐えやすいでしょう。
柱のピッチが狭いものを選ぶ
フェンスの柱(支柱)間の距離、つまり「ピッチ」は、フェンス全体の強度と安定性に影響します。
柱のピッチが狭いほどフェンスの強度は増します。標準的には2m程度のピッチが多いですが、隙間を狭くする場合は1m、大型犬の場合は50cm程度まで狭くするのもおすすめです。
また、ピッチが狭いと隙間が少なくなるため、外部からの視線を遮る効果も高まります。ただし、柱の数が増えるとその分コストも上がるため、予算とのバランスをふまえて検討しましょう。
脱走しないように隙間の狭いものにする
小型犬や痩せ型の犬種は、驚くほど狭い隙間から脱走することがあります。フェンスを選ぶ際は、パネル間や地面との間に犬が通り抜けられるような隙間がないか確認することが大切です。
犬の頭が通れる隙間であれば体も通ることができると言われています。格子状のフェンスの場合、横格子の間隔は愛犬の頭が入らない大きさにするべきでしょう。
また、斜面に設置する場合は、地形の変化によってフェンス下部に隙間ができないよう、地面に合わせた設計や施工が必要です。
取り付けた後のメンテナンス性の高いメーカーを選ぶ
フェンスは設置した後も、経年劣化や気象条件による損傷を防ぐためにメンテナンスが必要です。
アフターサービスが充実し、メンテナンス性に優れたメーカーを選ぶと、長期間フェンスの機能を維持できます。
メンテナンス性の高さを検討するには、下記のポイントをチェックすると良いでしょう。
- 部品の交換が簡単で自力でできるか
- 破損時の修理対応を受け付けているか
- 保証期間はどのくらいか
犬が頻繁にフェンスに接触する環境では、消耗が早まることがあるため、部品交換のしやすさは大きなポイントです。
犬のために庭に設置するフェンスのおすすめ商品3選
犬のいる家庭におすすめのフェンスを、3つ紹介します。
- LIXIL フェンスAB
- YKK AP シンプレオ フェンス
- 三協アルミ レジリア
それぞれに特徴があるため、自宅の環境や愛犬の特性、予算などに合わせて選択できます。
LIXIL フェンスAB
LIXIL フェンスABは、下部の隙間を従来の80mmから60mmに狭めた設計です。
オプションで「下桟すきまカバー」を取り付けられ、さらに隙間を狭くできるためペットの通り抜けを防止する効果が高まります。
アルミ製で軽量でありながらも強度があり、犬が体当たりしても簡単に変形しない堅牢さが魅力です。耐久性が高く錆びにくいため、メンテナンスも簡単です。
さまざまな高さのバリエーションがあり、犬種や運動量に合わせて選べます。
YKK AP シンプレオ フェンス
シンプレオフェンスは、水平ラインを美しく見せるデザインが施されており、フレームの露出を減らしたシャープな外観が特徴です。住宅の外観に調和しやすく、スタイリッシュな印象を与えます。
メタル製で非常に丈夫なため、長持ちし、犬が噛んでも破損しにくいです。デザインはシンプルでどんな住宅にも調和しやすく、高さや色も豊富なバリエーションから選べます。
隙間が狭いため目隠し効果が高く、犬が外に顔を出してしまうリスクも軽減できるでしょう。
三協アルミ レジリア
レジリアシリーズは、シンプルでありながらスタイリッシュなデザインが特徴です。横ルーバーや縦ルーバー、目隠しタイプなど、さまざまなデザインが用意されており、住宅の外観に合わせて選べます。
強化アルミ合金を使用しており、大型犬でも安心の耐久性です。風通しと視線の通りやすさを考慮した設計で犬が外を覗けるデザインもあり、ストレスを感じにくいよう配慮されています。
また表面処理技術が高く、長期間色あせや腐食に強い点が特徴です。通常80mmの下桟すき間は、オプション料金なしで15mmに変更できます。
フェンスを設置する際の注意点
フェンスの設置は簡単なように思えますが、実際には下記のような技術的課題や配慮すべきポイントがあります。
- フェンスを設置するブロックに厚みがないと追加で施工が必要になる
- 強度を上げるためには柱を埋め込む深さが必要
- フェンスを設置する場合は近隣の住宅に事前に告知をしておく
計画段階でこれらの点を考慮すると後々のトラブルを避け、満足のいくフェンス設置が実現できます。
フェンスを設置するブロックに厚みがないと追加で施工が必要になる
フェンスを既存のブロック塀や基礎の上に設置する場合、ブロックにはある程度の厚みが必要です。
厚みが不足している場合、支柱を安定して固定できず、風や犬の体当たりなどの力に耐えられない可能性があります。
厚みが足りない場合は、追加でブロックを積み増したり、コンクリート基礎を打設したりする必要が生じ、予想外の費用や工期の延長につながるでしょう。
また、古いブロックの場合は、強度が劣化していることもあるため、新たなブロックを積み直す可能性があります。
強度を上げるためには柱を埋め込む深さが必要
高さのあるフェンスや風の影響を受けやすい目隠しフェンスの場合、埋め込み深さが不足すると、強風によって倒れたり曲がったりするリスクが高まります。
柱を深く埋め込むほど、フェンスの強度が上がります。一般的に、30cm~50cmの深さが必要です。
安全性を確保するためには、地上部分の高さの3分の1以上の深さに支柱を埋め込むことが推奨されています。1.5mの高さのフェンスであれば、50cm以上の深さに埋め込みます。
大型犬や活発な犬を飼っている場合は、さらに深く埋め込むことで安全性が高まるでしょう。
フェンスを設置する場合は近隣の住宅に事前に告知をしておく
工事の期間や時間帯、どのような作業を行うのかを丁寧に説明しましょう。
フェンスの設置は、見た目や騒音などの面で近隣住民に影響を与える可能性があります。工事開始前に近隣住宅へ事前に告知し了承を得れば、近隣トラブルを未然に防げるでしょう。
騒音が発生する作業については特に配慮が必要です。また、境界線上にフェンスを設置する場合は、隣接する土地の所有者と境界確認すると安心です。
さらに、地域によっては、景観条例や建築協定などにより、フェンスの高さに制限がある場合もあるため、事前に確認することをおすすめします。
設置後も犬の吠え声などで近隣に迷惑をかけないよう、しつけや防音対策に配慮します。愛犬との快適な生活を続けるために、良好な近隣関係を維持しましょう。
犬を飼うならデッキを設置するのもおすすめ!

フェンスと併せて検討したいのが、ウッドデッキやタイルデッキの設置です。デッキは愛犬にとって快適な屋外リビングスペースになるだけでなく、飼い主にとっても犬との時間を楽しむ場所となります。
デッキは地面が濡れている日でも犬が泥だらけにならず、室内を汚すリスクが減ることがメリットです。素材に気を配ると犬の足腰への負担も軽減できます。
リクシルから販売されている「デッキDC」という直射日光によるデッキの温度上昇を抑える商品を活用すれば、犬の足裏、肉球のやけどを軽減する効果も見込めます。
デッキを設置する場合は、フェンスの色とデッキの色のコーディネートができるので、同じメーカーの商品を選ぶのがおすすめです。
フェンスで囲まれたデッキスペースは、まさに愛犬と飼い主のための特別な空間となり、バーベキューやガーデニングなどの趣味も安心して楽しめるでしょう。
犬のために設置するフェンスに関するよくある質問
犬のためにフェンスを設置する際のよくある質問と回答を、3つまとめました。
フェンスの高さはどのくらい必要ですか?
フェンスの適切な高さは、愛犬の犬種、サイズ、運動能力によって異なります。一般的な目安としては、下記の高さが推奨されています。
- 小型犬・愛玩犬の場合は60cm~120cm
- 中型犬・小型狩猟犬では1.2m~1.5m
- 中型狩猟犬・大型犬では1.5m~1.8m
- 大型狩猟犬・ジャンプ力の高い犬種では1.8m~
フェンスの高さだけでなく、フェンスの内側に踏み台になりそうなものを置かないよう注意が必要です。子犬の場合は、成長後のサイズや能力を見越して設計します。
フェンスに適した素材の選び方はありますか?
フェンスの素材選びは、耐久性、デザイン性、費用、愛犬の性格や行動特性を総合的に考慮することが大切です。
アルミ製は軽量で耐久性が高く、メンテナンスも簡単なため、多くの犬種に適しています。噛み癖のある犬や大型犬の場合、アルミ製や鉄製など強度の高い素材がおすすめです。
木製は見た目が自然で温かみがあり、プライバシーも確保できますが、噛む犬には不向きで、定期的なメンテナンスが必要です。
樹脂製は軽量で扱いやすく、水に強いという特徴がありますが、強い日差しにさらされると劣化が早まることがあります。
愛犬が外部からの刺激に反応しやすい場合は、視線を遮るタイプ(目隠しフェンス)が適しているでしょう。
費用を抑えて設置したいのですが、どのようにすれば良いですか?
フェンスの設置費用を抑えるには、下記の手段が有効です。
- DIY施工を検討する
- 設置範囲を必要最小限に抑える
- 複数の業者から見積もりを取る
- ショップのセール時期を狙って材料を購入する
価格の安い素材でDIYをすると、費用を抑えられます。また、愛犬が主に活動するエリアだけをフェンスで囲むことで、材料費を節約できるでしょう。
安全性や耐久性を犠牲にするような過度な節約は避け、長期的な視点でコストパフォーマンスの良い選択をすることがおすすめです。
まとめ
ペット、飼い主、近隣住民の安全で快適な住環境を作るために、フェンスは有効な選択肢です。
フェンスがあれば犬の脱走や交通事故のリスクを減らし、安心して庭で遊ばせることができます。フェンスを選ぶ際は、犬種や性格に合った高さと素材を選び、十分な強度と隙間の少ないデザインを選ぶことがポイントです。
適切なフェンスの設置は初期投資が必要ですが、愛犬の安全と家族の安心を考えれば、十分に価値のある投資といえるでしょう。
愛犬との幸せな時間を守るために、ぜひ理想的なフェンス環境づくりを検討してみてください。