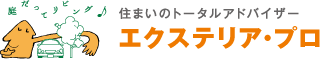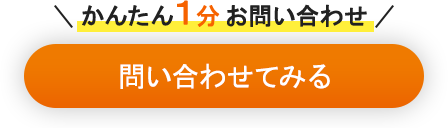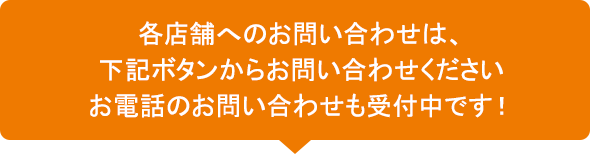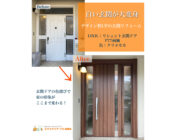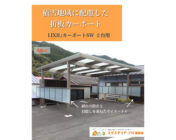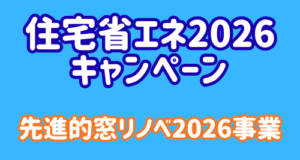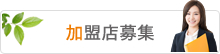ウッドデッキに目隠しのフェンスは必要?メリットや後付けの可否についても解説

ウッドデッキを設置したものの、隣家からの視線が気になったり、子どもの落下が心配だったりと、フェンスの設置を検討している方も多いのではないでしょうか。
ウッドデッキにフェンスを設置すると、プライバシーの確保や安全対策などさまざまなメリットが得られます。一方で、圧迫感や風通しの悪化といったデメリットも存在するため、慎重に検討する必要があるでしょう。
本記事では、ウッドデッキへのフェンス設置について、メリット・デメリットや選び方のポイントまで詳しく解説していきます。
ウッドデッキにおすすめのフェンスも紹介するので、フェンス設置で失敗したくない方は参考にしてください。
目次
ウッドデッキにもフェンスをつけるのがおすすめ

ウッドデッキを設置したら、フェンスも設置するのがおすすめです。
住宅密集地や道路に面した場所にウッドデッキがある場合、フェンスがあれば近隣の目を気にせずウッドデッキを活用できるでしょう。
子供やペットがいる場合、フェンスがあればウッドデッキで思い切り遊ぶことも可能です。
フェンスがあれば、プライバシーの保護や安全性の確保が実現し、ウッドデッキがさらに快適な空間になります。
ウッドデッキにフェンスをつけるメリット

ウッドデッキにフェンスを付けるメリットは、主に下記の3つです。
- プライバシーの保護ができる
- ウッドデッキからの落下防止ができる
- 日除け対策につながる
フェンスをつけると、ウッドデッキをさらに有効活用できるでしょう。
プライバシーの保護ができる
フェンスを設置すると、目隠し効果でプライバシーを保護できます。
フェンスが隣家や道路からの視線を遮るため、人目を気にすることなくウッドデッキでの時間を楽しめます。
洗濯物を干したり、子どもを遊ばせたりする際に人目が気にならなくなると精神的な負担もやわらぐでしょう。
夜間にデッキの照明をつけても隣人に迷惑をかけにくくなるため、夕涼みやバーベキューなど夜の時間も楽しめます。
目隠しフェンスを設置すると、ウッドデッキが真のプライベート空間として機能し、リラックスできる場所へと変わるのです。
ウッドデッキからの落下防止ができる
ウッドデッキにフェンスを設置すると、安全性を高められます。
地面から高さのあるウッドデッキは、落下事故のリスクが常に存在します。適切な高さのフェンスを設置すると、転倒や落下といった事故を未然に防ぐことが可能です。
小さなお子さんやペットがいる家庭では、フェンスがあると安心してウッドデッキを利用できるでしょう。
高齢者の方が、ウッドデッキを利用する際の手すりとしても機能します。
フェンスによって安全を確保できると、家族全員がウッドデッキを安心して楽しめるでしょう。
日除け対策につながる
フェンスは日除けとしての効果も期待できます。日除け効果によってウッドデッキ自体の劣化も抑制できるため、ウッドデッキの長期的な維持管理の面でもメリットです。
西日が強く当たる場所にウッドデッキがある場合、フェンスが日差しを和らげてくれるため、夏場の暑い時期でもウッドデッキを快適に利用できます。
ルーバータイプやラティスタイプのフェンスを選択すれば、適度な日除け効果を得ながら風通しも確保できるため、快適な空間を維持できるでしょう。
ウッドデッキにフェンスをつけるデメリット

一方で、フェンスの設置には下記のデメリットも存在します。
- 高さのあるフェンスは圧迫感につながる
- 風通しが悪くなる恐れがある
- ふとん干しには向かない
- 色が付く
- 強度が無い
デメリットを理解した上で、適切な対策を講じましょう。
高さのあるフェンスは圧迫感につながる
フェンスの高さが過度に高い場合、ウッドデッキ空間に圧迫感を与えてしまう可能性があります。狭いウッドデッキでは、圧迫感をはっきり感じるでしょう。
圧迫感によって、せっかくの開放的な空間が窮屈に感じられてしまうのは本末転倒です。また、高すぎるフェンスは景観を損ねる場合もあり、近隣住民とのトラブルの原因にもなりかねません。
適切な高さのバランスを見極め、プライバシー保護と開放感の両立を図ることが必要です。デザイン性を重視したフェンスを選ぶと、圧迫感が少なく目隠し効果も得られるでしょう。
風通しが悪くなる恐れがある
密閉性の高いフェンスを設置すると、ウッドデッキの風通しが悪くなる可能性があります。風通しが悪化すると熱がこもりやすくなり、快適性が損なわれてしまうでしょう。
また、湿気がこもりやすくなり、ウッドデッキそのものの劣化も促進される可能性があります。風通しの悪さは、カビや腐食の原因にもなりかねません。
ルーバータイプや格子状のフェンスであれば、プライバシーを保護しながら適度な風通しを確保できます。設置位置や角度を調整して、風通しをよくするのもおすすめです。
ふとん干しには向かない
ベランダの柵のようにふとんを干したいという方もいるかと思いますが、ウッドデッキに設置するフェンスは大きな重量による負荷がかかる想定では作られていません。
そのため、ウッドデッキのフェンスはふとんを干すことには向いていないです。
もし、風通しの良いウッドデッキでふとんを干したいなら物干し台を設置するのがおすすめです。
色が付く
木材や塗料から衣類に色移りしてしまうことがあります。そのため、フェンスに寄りかかった際にお気に入りの洋服が汚れることもあるでしょう。
もちろん、色が付かないものもありますが、使いはじめの製品や経年劣化で色落ちをしてきている製品などは色移りのリスクがあるので、注意してください。
強度が無い
ウッドデッキへ設置するフェンスは大きな衝撃などに耐えられるように設計されているわけではありません。
そのため、子どもやペットが遊んでいてフェンスにぶつかってしまうと、フェンスが壊れてしまったり、フェンスの形状が変化してしまったりする恐れがあるので注意しましょう。
ウッドデッキにフェンスの後付けは可能
既存のウッドデッキにフェンスを後付けすることは可能です。専用の取り付け金具やブラケットを使用すれば、比較的簡単に設置できるでしょう。
ただし、ウッドデッキの構造や材質によっては、補強工事が必要になる場合もあります。DIYでの設置も可能ですが、安全性を考慮すると専門業者に依頼するのがおすすめです。
後付けの場合、既存のウッドデッキとの調和を考慮したデザインを選ぶと洗練された印象になります。建築基準法や地域の条例に適合しているフェンスを設置しましょう。
ウッドデッキに設置するフェンスの選び方
ウッドデッキに設置するフェンスを選ぶ基準は、主に下記の4つです。
- 目的に合わせた高さで選ぶ
- 耐久性などを考慮した素材を選ぶ
- 種類ごとのメリットで選ぶ
- 設置にかかる費用で選ぶ
複数の基準を総合的に考慮して、目的や好みに合ったフェンスを選びましょう。
目的に合わせた高さで選ぶ
適切なフェンスの高さは設置目的によって異なります。プライバシー保護が主な目的の場合、1.8〜2.0メートル程度の高さが効果的でしょう。最近は高尺のフェンスが好まれる傾向があります。
安全対策として設置する場合は、1.1〜1.2メートル程度でも十分な効果が期待できます。子どもの落下防止が目的であれば、子どもの身長や年齢を考慮した高さを選びましょう。
地域の条例で高さ制限がある場合は、フェンスの目的と法的制限のバランスを取りながら高さを決めます。
耐久性などを考慮した素材を選ぶ
メンテナンスの頻度や費用を考慮し、総合的にコスパのよいフェンスを選ぶことも大切です。
デザイン性を重視して、頻繁な手入れが必要なフェンスを選ぶと長期的なコストパフォーマンスが低下します。
たとえば天然木材は自然な風合いが魅力ですが、こまめなメンテナンスが必要です。
一方人工木材やアルミ材は耐久性に優れ、メンテナンスの手間が少なく扱いやすいでしょう。樹脂製のフェンスは軽量で施工しやすく、色褪せにも強いため長期間にわたって機能を維持できます。
地域の気候条件や海沿いなどの環境要因も考慮に入れて、長期的なメンテナンス費用も含めたコストパフォーマンスで判断しましょう。
種類ごとのメリットで選ぶ
各フェンスのメリットが、目的に合っているかを基準に選ぶのもおすすめです。
費用やメンテナンスコストを抑えたい場合は、メッシュフェンスがおすすめです。目隠し効果と風通しを両立させたい場合は、ルーバータイプが良いでしょう。
日当たりを重視する場合は、ポリカーボネートフェンスにすると日光を遮りません。
フェンスの機能、設置する場所の雰囲気や住宅の外観との調和を考慮して選ぶと、失敗が少ないでしょう。
設置にかかる費用で選ぶ
フェンスの材料費と施工費で選ぶ方法もあります。
フェンスは素材やオプション追加で価格が異なり、設置費用は業者ごとに幅があるため、複数の素材や業者で見積もりを取るのがおすすめです。
量販店で売っている既製品のフェンスをDIYで設置する場合は、費用を大幅に抑えられるでしょう。オーダーメイドのフェンスは価格が高くなりがちです。
長期的な視点で考えると、初期費用が高くても耐久性に優れた製品の方が結果的にコスパがよいこともあります。
価格だけでなく品質やアフターサービスも比較検討すると、トータルコストを考慮したフェンス選びができるでしょう。
ウッドデッキにおすすめのフェンス3選

ここからは、ウッドデッキに設置する場合におすすめのフェンスを3種、厳選してご紹介します。
- LIXIl ウッドパーティション
- ヴィラウッドフェンス メッシュフェンス
- リウッドデッキフェンス 3型
機能や費用感を比較して、ご自身に合ったフェンスを選択してください。
LIXIl ウッドパーティション
ウッドパーティションは、自然な木の風合いを持ちながらも、耐久性に優れた人工木材やアルミ形材を使用して見た目の美しさと機能性を両立させています。
カラー展開も豊富で、グレーウッドやダークウッドなど、さまざまな外観に合わせた選択が可能です。
2025年から発売された新製品で、高さは最大1.8mまで対応しており、大人が立ち上がった際にも目隠し効果が維持できます。
人工木材であるため定期的な塗装やメンテナンスが不要で、手間をかけずに美しい状態をキープしやすいでしょう。
必要な部品がすべて揃ったフルセットとして販売されており、DIYでの設置が可能です。ほかのウッドデッキやエクステリア製品と組み合わせて、より個性的な空間を演出できるでしょう。
ヴィラウッドフェンス メッシュフェンス
三協アルミのヴィラウッドフェンスは、ペットのいる家庭におすすめのフェンスです。
人工木材を使用しているため、定期的な塗装やメンテナンスが不要で、長期間にわたって機能性を維持できます。
メッシュデザインは視認性が高く、開放感や風通しのよさは抜群です。
高さが1.2m、デッキとの隙間が50mmと狭いため、ペットの逃げ出しを防ぐ効果が高く、小型犬などのペットを飼っている家庭におすすめです。
門扉のようになっていてフェンス内を開鎖できるため、ペットの逃げ出しも防げるでしょう。
リウッドデッキフェンス 3型
リウッドデッキフェンス 3型は、125mm幅の平板を横に取り付けた横スリットデザインで、視覚的な開放感を保ちながらもプライバシーを確保できるフェンスです。
高さは800mmから1400mmまで選べるため、ウッドデッキの高さに応じて最適なサイズを選択できます。
素材は再生木材(リウッド)を使用しており、環境に優しいだけでなく、耐久性にも優れています。樹脂とスチールの組み合わせで腐食や劣化に強く、長期間にわたって美しい外観を保てるでしょう。
リウッドデッキフェンス 3型は切り詰め加工が可能で、必要なサイズに合わせて取り付けられます。
ウッドデッキのフェンスに関するよくある質問
ウッドデッキのフェンス設置を検討する際によく寄せられる3つの質問について、詳しく回答していきます。
ウッドデッキに柵を設置する際の法律・条例はありますか?
建築基準法では、フェンスや柵の高さに関する具体的な制限が設けられています。ブロック塀の上に設置する場合の高さは、ブロックの高さとフェンスの高さが合わせて2.2メートル以下です。
2階以上のバルコニーや屋上に設置する場合は、手すりや柵の高さが1.1メートル以上であることが求められます。
自治体によっては町の景観を守るために独自の条例を定めていることもあるため、設置前に確認が必要です。
マンションやアパートの場合は、管理規約によってフェンス設置が制限されている可能性があります。
小さい子どもやペットの安全対策になりますか?
適切に設置されたフェンスは、小さな子どもやペットの飛び出し防止など安全対策として有効です。
適切なフェンスの高さは子どもの年齢や身長によって異なり、幼児の場合は1.2m以上の高さが推奨されています。
また、フェンスの隙間から手や足が抜けないよう、格子の間隔にも注意が必要です。
ペットの場合は、ペットの運動能力や体長に適したフェンスを設置すると、ペットのケガや近隣トラブル防止効果が高まります。
小型犬であれば比較的低いフェンスでも効果的ですが、大型犬の場合はより高く、頑丈なフェンスが必要になるでしょう。
台風や強風に耐えるためにはどれくらいの強度があると良いですか?
フェンスの耐風圧強度は、通常30m/sから50m/sの範囲で設計されていますが、台風対策としては41m/s以上の耐風圧強度を持つ製品を選ぶことが推奨されています。
台風が頻繁に来る地域では、42m/s以上の耐風圧強度を持つフェンスが望ましいでしょう。
アルミやスチール製のフェンスは、強度が高く、耐久性にも優れているため、台風対策に適しています。
フェンスの高さや支柱の間隔も重要です。支柱の間隔を狭くすると、全体の強度が増して強風に対する抵抗力が高まります。標準的な間隔は1.8m〜2.0mですが、風の強い地域では1.5m以下に設定してもよいでしょう。
隙間の多いデザインやメッシュタイプ、ルーバータイプのフェンスは、風通しがよく風圧を軽減できます。
まとめ
ウッドデッキにフェンスを設置することで、プライバシーの保護、安全性の向上、快適性の確保など多くのメリットを得られます。
ただし、圧迫感や風通しの悪化などのデメリットもあるため、隙間のサイズや高さを慎重に選んで住宅の外観や機能を損ねないようにしましょう。後付けも可能ですが、法的な制限や近隣への配慮を忘れずに。
素材・高さ・デザインといった要素を総合的に検討し、長期的なコストパフォーマンスを見据えた計画を立てましょう。必要に応じて専門業者に相談しながら進めると、満足度の高いウッドデッキ空間を実現できます。