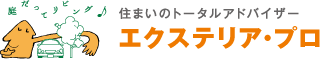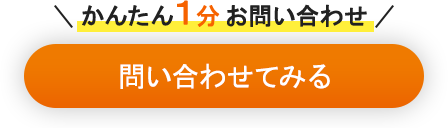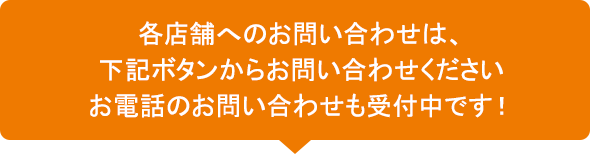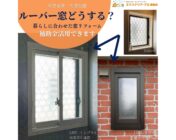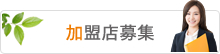フェンス設置で気を付けたい! 近隣トラブルと対策について

最近、設置が増えているフェンスは、プライバシーの確保や防犯対策、美観の向上など、さまざまな目的で行われます。しかし、設置にあたっては前もって考えておくべき点や注意点が数多く存在します。ここでは、フェンスを設置する際に気を付けたいポイントをご紹介します。
境界線の確認は基本中の基本

フェンスを設置する前に、最も重要なのは土地の境界線の確認です。境界を誤って認識して設置してしまうと、隣地への侵害となり、隣人との関係にヒビが入る原因になります。設置前には必ず測量図を用意し、境界標識と照らし合わせて確認を行いましょう。
一般的には、境界には、通常コンクリート杭や金属プレートなどの境界標が設置されています。設置されている場合は、その位置を確認します。ただし、年月が経つと境界標が移動してしまうことがあるため、慎重に確認する必要があります。
もしも自宅の境界が曖昧な場合は、隣の敷地の持ち主と相談し、土地家屋調査師に調査を依頼すると良いでしょう。
法律・条例のチェック

意外に見落としがちなのが、法的な制約です。地域によっては、フェンスの高さやデザインが条例によって規制されている場合があります。そのため、自治体の建築基準法や条例を事前に確認し、適合させることが大切です。特に防火地域や景観地区に指定されている場所では、より厳しい基準が設けられていることもあります。
建築基準法におけるフェンス(塀)の設置に関する具体的な規定は、フェンスの材質やデザインに直接触れるものではありませんが、一般的に関連する条項は以下のようなものです。アルミフェンスに直接該当する内容はないため、塀全般のポイントを以下にまとめます:
1. **高さの制限**:
– 塀またはフェンスの高さには制限があり、基本的には2.2メートルを超える場合には構造計算が必要です。地域によってはさらに厳しい制限があることもあるので、自治体の基準を確認する必要があります。
2. **構造の安全性**:
– 塀の安全性に関しては、地震や台風など自然災害に耐えるような構造が求められます。特に、塀の高さが高い場合や密集地域ではより安全な設計が必要です。
3. **設置場所の制限**:
– 設置場所によっては、道路斜線制限や日照、風通しに関する制限がかかることがあります。
4. **境界からの距離**:
– 隣地との境界から離さなければならない距離が規定されている場合があります。これも自治体の規定を確認します。
5. **耐火性能**:
– 一部の地域や用途地域では、防火地域における耐火性能が求められることがあります。
これらの基準はフェンスの設置において基本的な部分であり、詳細や地域による違いがあるため、具体的な計画を立てる際には、地元の建築基準や条例を確認することが重要です。また、特定の状況や場所においては、専門家に相談することをお勧めします。
県や市の建築指導課等でも丁寧に教えてくれたりする窓口もありますので、ご利用をおすすめします。
隣人への配慮とコミュニケーション

フェンスの設置は、隣人との関わりが避けられません。お隣さんとの関わりが少ない現代では、交渉が憂鬱なこともあるかもしれません。しかし、古い塀を放置したことにより、塀が壊れて被害を与えてしまった場合のリスクもあります。事情をきちんと相談し、家のメンテナンスを適切に行うこともトラブル回避には重要です。
その他、設置によって隣地の日照や風通しが悪くなるケースや、デザインが周囲と調和せず不快感を与えることもあります。事前に隣人へ設置計画を伝え、意見を伺うことでトラブルを未然に防ぐことができます。お互いに納得した上で進めることが、良好な関係を保つ秘訣です。
長く快適に生活するためにはこういった配慮が大事ですね。
デザインと機能性のバランス

フェンスは実用性だけでなく、住宅の外観にも大きく影響を与える要素です。プライバシーを重視するあまり無機質なデザインにすると、圧迫感を感じさせることがあります。また、耐久性に優れた素材を選ぶことも重要です。価格を重視するあまり、設置後に歪みが出てしまった、音鳴りがするといったトラブルも発生します。地域の環境に適した素材を選び、メンテナンスの手間を省けるように工夫しましょう。
一般的には住宅の玄関の色、アルミサッシの色、門扉の色と合わせたり、木目で設置することが多く、家全体の印象を上げることが可能です。
将来的なメンテナンスを見据えて

設置したフェンスは、年数が経つごとに劣化することがあります。そのため、将来的なメンテナンスのしやすさも考慮に入れて設計することが賢明です。特に、アルミフェンスなどは錆びに強い反面、強風や地震に対する耐久性が設計上どうなっているかを確認することが重要です。
代表的な実例としては、2018年に発生した「大阪府北部地震」があります。この地震では、震源地に近い地域で大きな被害が報告され、その中の一例として高槻市の学校に設置されていたブロック塀の倒壊がありました。この倒壊によって、通学途中の女子児童が亡くなるという痛ましい事故が発生しました。
この事故は、多くの自治体や学校で設置されているブロック塀の安全性について見直すきっかけとなり、ブロック構造物の耐震性や適切な施工、老朽化した構造物の点検といった課題が大きくクローズアップされました。この事件を受けて、全国的にブロック塀の安全点検や耐震補強が推進されるようになりました。
フェンスの設置は一度行うとなかなか変更することが難しいため、計画段階から慎重に進めることが求められます。境界の確認や法令のチェック、隣人とのコミュニケーションをしっかり取ることで、トラブルを未然に防ぎ、美しい住環境を実現しましょう。
2025年速報! おすすめフェンス

2025年春に魅力的なフェンスが新発売されます。
一番のオススメは業界ナンバーワンLIXIL製のフェンスABにブロック上施工に高さ1.4メートル、1.6メートルタイプが発売されることです。
ポイントは今までは高さ1.4メートルのフェンス設置する場合、2段更に柱の間隔も1メートルピッチになっていたのが、今回強度設計が強化され、1段、柱間隔も2メートルピッチになり、すっきりしたデザインに刷新されたこと。柱の設置本数が約半分、上下つなぎ合わせる施工もなくなり、施工費も安くなったことです。
しかも価格設定も業界で最安値に設定されております。期待したいですね。